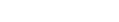05 10月 安全な指導とアジャストのために大切なこと
「ヨガのアジャストってどうすればいいのだろう?」 指導者の方は、そう悩んだことはありませんか。 例えば、ダウンドッグが台形になってしまったり、 苦しそうにポーズをとっている生徒さんがいたとします。 生徒さんのお尻を押してみたり、ひいてみたり, 教わったとおりのアジャストをしても、たいていはうまくいかなし、 伝わらない。 生徒さん一人一人が異なり、状態もやろうとしていることも、 今日これからやることもあなたとは違います。 だから、同じダウンドッグのポーズのようでも、 一人ひとりの身体の可動域も思っていることもちがいます。 アジャストを安全に行うには、まずあなたがダウンドッグに対する理解と さらに生徒さんの動きを観察するスキルが必要になってくるということです。 でも、それに気づけたとすれば、それは素晴らしい成長と学びのチャンスです! 百人いれば百通りのヨガある。 ~一人ひとりを尊重するアジャスト~ 生徒さん一人一人はみんな違う人生を生きてきて、 違う体を持って生きています。 私が思う指導者のアジャストとは、その生徒さんがやりたいことに寄り添い、 道のりを一緒に探すお手伝いをすることだと思います。 もしかしたら、必要がないこともあるかも知れません。 なぜなら、時間をかけて生徒さんは自分のやり方を 必ず見つけていくものでもあるからです。 一つしかやり方がない、形はこれだ、と決めるのではなく、 その生徒さんの望み、そのときに進みたい分だけが 進めるようなお手伝いをする、アジャスト(直す、正す)より サポート(お手伝いする)を基本精神に考えたいところです。 1.「正そう」とすることの危険 ヨガポーズの「形」は、実はその前にどんなふうに動いたか、 その前の動き次第で形は決まります。 もし完成形がおかしくても、それは一人一人の生徒さんが 動いた結果であり、生徒さんの気持ちや願いから出てきた動きによるものです。 怖かったり、不安だったり、よくわからなかった、 普段使いなれないからだの使い方をしている、 それぞれの事情で生徒さんが個々の事情で動いた結果なのです。 だから「形」を直そう、という考えは過去を変えようとするような、 不自然な結果を生みます。 さらに「正そう」とその人の気持ちに敬意を払ってないアジャストは、 生徒さんを緊張させ、しばしば怪我を生む結果になります。 自分も含めて、沢山のヨガをする生徒さんたちが、こういうアジャストで 怪我をして長いこと苦しんできたのを私は見てきました。 そこで、まず大事にしてほしいのは、あなた自身の直感と、 一人ひとり違う生徒さんへのリスペクト(敬意)です。 それさえあれば、ポーズのプロセスはだんだんとわかってくるし見えてきます。 ポーズには必ずやり方があり方向性があります。 疑問さえ持ち続ければ、 生徒さんもあなたも、 人には学ぶ力もありますし、 こたえが今なくても、常に「なぜだろう?」と問えていれば大丈夫です。 必ず動きについての理解も深まり、あなたが望むレッスンもできるようになるのです。自分を信じていきましょう! 次回は、いよいよダウンドッグの動きの観察方法、アジャストについても書いていきますので、お楽しみに! ************************ 銀座ATヨガ体験day ~安全で痛みのないヨガと身体を手に入れるために~ 痛みのないアーサナを手に入れる ~アレクサンダー・テクニークヨガ(ATヨガ)~体験はこちらから ...